
1965 東京芸術大学 入学(美術学部・建築科 )
事務所 神谷武夫建築研究所 E-mail:kamiya@t.email.ne.jp |

QUOTATIONS from BOOKS
| 語 録(本からの抜粋) |
| 日本の語録 | 西洋の語録 | 東洋の語録 |

| 本の思い出、絵の思い出 |

暗く 鬱屈した青春時代を過ごした者にとって、高校時代が楽しかった と回想することはできない。生まれて来なければよかった、と早くから考えるような人間であった。けれど そうした苦悩や不安にさいなまれながら、なお 未知への憧れを心に抱きつつ生きるというのもまた、青春時代の 一つの形であるのかもしれない。外界との違和感を 常に感じながら 内向していく若者が、しばしば 読書や芸術に救いを求めるように、私もまた 毎日 美術室に入りびたって 絵を描き、そうでない時には(授業中も)小説ばかり読んで過ごしていた。母校に対して 何よりも感謝しているのは、そうした生活を可能にさせてくれるような「自由」にあった。管理されることを嫌い、集団で行動することを苦手とする故に、今もなお宮仕えせずに フリーでいるくらいだから。
三年間の担任は 国語の内田先生であったが、美術部では ずっと林先生の指導を受けた。建築家になろうと決心した直接のきっかけは 林先生の勧めであったが、文学の方の影響も少なくなかった。当時愛読していた立原道造が、詩人であると同時に 建築家でもなかったら、建築家になろうとは 思わなかったかもしれない。また 北園へ入って最初に読んだ小説『ジャン・クリストフ』に深く感動したあまり、自分も ジャン・クリストフのように生きねばならぬ、などと心に決めたりしたのだった。貧乏芸術家の道と 独身生活は、ここに胚胎しているわけである。
一方、美術と文学を結びつけた大きな出会いは、国語の教科書に載っていた「窓の少女」という一文である。これは 美術史家、矢代幸雄が欧州に留学し、ロンドンのダリッチ画廊にある レンブラントの『窓の少女』という絵に寄せて内面を語ったもので、高校時代に出会った文章の中では、中勘助の『銀の匙』と並んで 最も美しいものであった。文章の美しさばかりではない、そこに論じられている レオナルド、ボッテイチェリ、レンブラントを通して語られる その芸術論と人生論とに深い共感と、暗い人生における慰めさえ覚えたのである。
  その「窓の少女」は 矢代幸雄の最初の美術評論集『太陽を慕ふ者』に収められていると知ると、戦前に改造社から出たその本を 神保町や本郷、早稲田の古書店をどれだけ捜しまわったことだろうか。いくら尋ねても見つからずに 半ばあきらめかけていた頃、別の本を捜している時に 不意に眼にした時の驚きと喜び。それは 美術評論集というよりは、若き日の芸術の徒が、遥かな異国の地でつづった 魂の漂泊の日記であった。真摯な学問と芸術の探求に ないまぜにされた感傷主義の故に、著者はそれを絶版にして 人目から遠ざけてしまったのだが、若い私にとってその本は 一種の精神的な救いと慰謝であった。
「あくがれなくて 如何して人の生きられやう。是は太陽を慕ふものの声である」と書き出されたこの書を読み終わった時、私の心の中には 勃然として、「自分もこのような本を作ろう」という気持ちが 湧き起こったのである。それからは 日に夜を継いで本作りに熱中し、あちこちに書き散らした原稿や詩、日記、手紙の類まで動員して文章を集め、用紙を選んで清書し、たくさんの図版を貼り込み、製本して キャンバス装の表紙をつけ、北園の校舎のスケッチを描いた函まで造ったのだった。こうして私の初めての本、美術評論集『ルノワールの涙』限定1部が できあがったのである。当時 少数の師友に見せ、その時書いてもらった感想文は 今でも保存してある。しかし その本自体は、書棚にしまったまま 10年以上も 手を触れていない。その文章の多くが あまりにも幼く感傷的であるために、顔から火が出るようで 読めないからである。
 『窓の少女』 に関しては、いつか英国に行くことがあったら きっとこの絵を訪ねよう、という当時の願いが、その 10年後に叶えられた。ロンドン郊外のこの画廊のことは 知る人少なく、苦労の末に やっとたどり着いて、私の青春時代の象徴のような その絵と対面したのである。その時、何だか 私の心に漂い続けていた青春の想いに 別れを告げられたような気がした。それが、私にとっての「歌のわかれ」だったのだろうか。

BANK NOTES & COINS in SHOWA
 父が生前にくれた 名刺用の青いプラスチックの箱の中に、昭和の 戦中・戦後 の 紙幣と硬貨が、わずかな量ですが、たたんで入っていました。今から見れば珍しい アンティークの「近代日本の お金」です。あまりに少なすぎる分量の「少額貨幣」ですが、物珍しく思う方もいるでしょうから、それらをスキャンして 載せておくことにしました。 ここをクリック すると『 昭和、戦中・戦後の 少額貨幣』のページに飛びます。 ( 2024 /05/ 01 ) |

インタビュアー:佐藤雅子(インド舞踊家)
プレス・リリースは、9月3日に インド政府の 文化・観光省により ニューデリーの アショカ・ホテルで行なわれ、その後、9月13日には ムンバイで出版記念会が開催され、各地で たいへんな話題を呼んでいます。 今回のインタビューは、日本でインド建築についての ご研究をしていらっしゃる わずかな一人である 神谷先生に、インド建築についての お話を うかがいました。
 の Book Review ・ の Book Review ・
当時、私は、東京芸術大学の美術学部・建築科を卒業後、山下和正建築研究所に入り、青山の フロムファースト・ビル の設計を担当していましたが、アジア的感覚が すっぽりと抜けてしまう建築界の風潮に 多少の反発を覚えていました。何かアジア的な 新しいものを作ることはできないか? と、考えていたところ、「インド」という国が突然 頭に浮かびました。 子供時代に親しんだ 花祭りや三蔵法師、手塚治虫の漫画など、仏教を通じたものが 日本の文化に根付いていること、敬愛する埴谷雄高や 高橋和巳が インドのジャイナ教に興味を持っていたこと、当時はFM放送が始まった頃で、小泉文夫による「NHK 世界の民族音楽」を聴いて 日本人の若者がインドに行き始めていたこと などが重なりました。
早速 インドに関する文献を集めましたが、仏教の本は多いものの、建築に関する本は ほとんどなく、観光ガイドブックも インド、ネパール,スリランカを一緒にした 薄い本一冊のみ。とにかく この目でインドの建築物を見なければならないと、フロムファースト・ビルの竣工後、事務所を辞め、1975年1月に、3ヶ月の滞在予定で インドの地を踏みました。
「何でも 人と同じことをしなければならない」日本に比べ、「思いのままで OK」 というインドは、どんな格好をしても OK、自己主張をして波風をたてても OK、「生きていること」を まったくもって実感でき、次から次へと 新しい発想が沸いてきました。3ヶ月後に日本に戻りましたが、この時のインド旅行は たいへんなインパクトを与え、さらに深くインド建築を調べてみよう と思ったのです。

インド建築の代表として 私が一番に挙げたいものは、西インドのラーナクプルにある ジャイナ教の「アーディナータ寺院」です。内外部を装飾する彫刻の造形美は ヒンドゥ寺院のそれには及びませんが、寺院全体の壮麗さは 他の追随を許しません。それは、先ほど述べた、三つの建築形式の総合性からきています。ウダイプルから車で4時間の山中にあり、あまり知られていない寺院ですが、訪れるたびに 感動を覚えます。インド建築の 最高傑作でしょう。
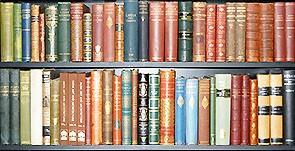 書棚の一部 書棚の一部
今から7年前に発行された『 インド建築案内 』には、神谷先生がそれまで 20年間に渡って撮影した2万枚もの写真の中から 1800枚が選ばれ、収集した資料の中から 300枚の地図と図面が使用されています。既に初版1万部、第2版 5,000部が売り切れ、第3版がこの春に刊行されました。

ラーナクプルの アーディナータ寺院を インドで最も優れた建築と絶賛していらっしゃる神谷先生の、その他の お薦めのインド建築は、北インドのヒマーチャル・プラデシュ州にある 木造寺院群。 多雨で緑が多く、また複雑な地形から 観光化が殆ど行われていない ヒマラヤの山岳地帯は、他地域とは異なる文化を呈示し、建築学的に見ても たいへん興味深いのだそうです。 お好きなインド料理は、タンドーリ・チキンと バター・ナーン。インドに行くと必ず 各地で召し上がるそうです。 お薦めは コルカタの リットン・ホテルの ビーフステーキ。インドでは最高なのだそう。 お好きな言葉は、
「 私は、我々をとりまく全世界が たとえ滅びようと、その中に 救いを見いだし得るような、独立した 自主的な生活を始めるように 忠告しているのだ。」 「 サイの角のように ひとり歩め 」 (ブッダの言葉) 黙々とご自身のお仕事に専心されてきた 神谷先生の生き方を表しているような言葉 にも感じられます。 毎日心がけていらっしゃることは、 「 規則正しい生活 」。 インドの建築にふれることによって、それまで 欧米と日本という二元論で考えていた世界を、多元的に見るようになり、世界は多様性に満ちている という認識を深めるようになられたという 神谷先生。 現在は、ご自身の研究とお仕事の他に、専修大学の非常勤講師として、芸術学と 建築を教えていらっしゃいます。
19世紀の建築の理念は「様式」、20世紀の建築の理念は「空間」と言われています。 現代建築は、幾何学で作られ 内部空間の美しさを重視する 皮膜的建築(イスラム建築)と相性が良く、講義などをしても人気があるそうですが、これとは趣を異にして 外観の「彫刻性」を重視したインド建築は、現代には なかなか受け入れられにくい要素を持っています。

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp
|






