ALEXANDR GERZEN
| アレクサンドル・ゲルツェン |
神谷武夫
| アレクサンドル・ゲルツェン |
神谷武夫
ナロードニキの元祖とも呼ばれる アレクサンドル・イワーノヴィッチ・ゲルツェン (1812- 1870) は、ナポレオンが侵入した その年に モスクワで生れた思想家・文学者であって、後にヨーロッパに亡命して 長く ロンドンに住み、1852年から この回想録『過去と思索』の執筆を始めた。精彩のある筆致で 幼少時代から巻を追って書かれ、全部で8巻にも及んだ。私の学生時代には その約 85パーセントが金子幸彦によって日本語に翻訳されていて、筑摩書房の「世界文学大系」の第 82、83巻の2冊に収録されていた。この分量がトルストイの『戦争と平和』に ほぼ同じという、まことに長大な回想録なのであるが、しかし これは退屈に長たらしいものではない。

小説とちがうのは、それが単なる物語ではなく、ロシアの帝政時代の社会の描写や 知識人グループでの交流、ロシアやヨーロッパの傑出した人物たちの事績と その評価などが、かなりの分量で描かれていることである。それらの人物とは、たとえば生涯の親友となった 詩人の オガリョーフ(この回想録は オガリョーフに捧げられている)、文芸評論家の ベリンスキー、歴史家の グラノフスキー、アナーキストの バクーニンなどで、彼らとは深い友情で結ばれ、モスクワのサークルで切磋琢磨しあった。ヨーロッパに移ってからは、革命と動乱の 19世紀中葉に 新しい精神で時代を生き抜いた人々、イギリスの ロバート・オーウェン、イタリアの ガリバールジや マッツィーニ、フランスの ルイ・ブランや ルドリュー・ロラン、そして アナーキストの プルードン などとの交流が語られる。
ロシア革命以前のロシアには 帝政が敷かれていて、皇帝(ツァーリ)が絶対権力を握っていた。ナポレオン侵入時の皇帝は アレクサンドル1世で、これは 若い時には自由主義者でもあった穏健派だったが、1825年に旅先で急死すると、悪名高い専制君主 ニコライ1世が帝位につく。 このとき 14歳にすぎなかった少年ゲルツェンは 精神的に目覚め、デカブリストたちの "反・専制" と "反・農奴制" の意思を 引き継ぐことを決意する。そして 生涯の友となるオガリョーフとともに、モスクワの街を一望のもとに見下ろす 雀が丘で、1828年に その誓いを結ぶ。2人は この "雀が丘の誓い" を一生 裏切ることなく 活動をし続けた。この丘こそ、ナポレオン軍がその麓から退却を始めたことを記念して、アレクサンドル帝が カテドラルとしての「救世主聖堂」を建設すべく コンペを開催した、その敷地(ヴァラビョーヴィ丘)である。

長じて モスクワ大学に入学すると、ゲルツェンは 理数学部で自然科学を熱心に学ぶ一方、学生運動に挺身した。ツァーリズムの圧制のくびきに反抗して 自由思想や立憲思想の論文を書いたりもしたので、卒業後の 1834年に突然逮捕される。友人のオガリョーフたちも逮捕され、翌年、欠席裁判のまま シベリア送りとなる。といっても ゲルツェンは貴族であったから 肉体労働をさせられたわけではなく、シベリアの入口にあたる ヴャトカという町(現在のキーロフ)で官吏の仕事をさせられたのである。モスクワの刺激に満ちた生活から切り離されて無聊(ぶりょう)をかこったが、2年半後には ずっとモスクワに近い ウラジーミルに移され、ある程度 快適な生活を送るようになる。ここで彼は 情熱的行動家としての一面を 大いに発揮させる行動をとることになる。
モスクワ大学を卒業したあと 22歳のある日、まだほんの子供だとばかり思っていた従妹が 美しく成長しているのに出会う。当時 17歳のナターリヤ・ザハーリナで、二人は墓地を散歩しながら尽きせぬ話をし、「また あした」と言って別れる。ところがその翌日、二人が再び会う前に ゲルツェンは逮捕されて留置場に入れられてしまうのだった。ヴャトカに流刑になっていた間、二人は 絶えず手紙を書きあって心を通わせ、愛しあうようになる。ナターリヤは 早くに両親に死なれて叔母の公爵夫人に引き取られ、孤独な生を生きていたうえに、意に染まぬ結婚を強いられて 絶望の淵に沈む。

その 2年後、やっと流刑を解かれてモスクワに戻ると、オガリョーフなど かつての仲間や、ベリンスキーなど 新しい友人たちと知的なサークルを作り、ロシアの悲惨な状況や 将来の改革を論じ合う。このころ モスクワの論壇を支配していたのは ヘーゲル哲学であった。ヘーゲルは その数年前に世を去っていたが、後期のヘーゲルは 功なり名とげて ドイツ哲学界の権威となり、体制内保守派になっていた。ゲルツェンは 彼の哲学に大いに影響を受けるものの、次のようにも書く。(『過去と思索』 からの引用は茶色で示し、すべて 金子幸彦と長縄光男の訳による)
彼は、後にマルクーゼが『理性と革命』(舛田啓三郎・中島盛夫・向来道男訳、1961、岩波書店)で論じたような、"若きヘーゲル" の支持者であり、「現実が まだ理性的でないならば、それを 理性的なものに変革すべきである」という立場だった。 そうした中、ゲルツェンのサークルで 長く語り継がれる有意義なできごとは、友人の歴史家・グラノフスキー (1813-55) による モスクワ大学公開講座であった。その「フランス・イギリス中世史」において、大学講堂を満員にした婦人たちや社交界の人々を前にして、グラノフスキーは 暗く抑圧された中世の社会を淡々と語ることによって、それと重ね合わせるように 帝政ロシアの現実を浮き彫りにし、圧制への深い抗議をしのばせたのである。それは
講義のあとで、ゲルツェンとグラノフスキーは 手をとりあって泣くのである。 1847年の初めに ヨーロッパに移ったゲルツェン一家は まずパリに住み、秋にはイタリアへ渡る。その翌年の2月にパリで二月革命が起こり、王政を倒して第二共和制が成立すると、ゲルツェンは驚喜してパリに向かう。ところが 5月にゲルツェンがパリに着いた時、革命はすでに失敗に終り、6月には 軍によって民衆が虐殺されていく姿を まのあたりにする。"遅れた" ロシアを脱出した西欧派のインテリゲンチャが ヨーロッパで見たものは、やはり "野蛮" と "残虐" であった。ヨーロッパへの幻想は 棄てられなければならなかった。ゲルツェンが一生の課題として再確認したのは、ほかならぬロシアの民衆(ナロード)、抑圧された農奴の解放であり、人間の自由と尊厳の確立であった。 このあと ゲルツェンには つらい試練の時、『過去と思索』第42章に書かれることになる「家庭の悲劇の物語」に直面する。母と次男が海難事故にあって死亡、翌年には妻のナターリアが 別の男との愛情のもつれの後に、ついに産褥で死ぬ。ヨーロッパの名目上の "民主主義" への絶望と 家庭の悲劇とは、ゲルツェンに深い悲哀感をもたらした。
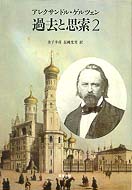
その年に(1852年)彼はロンドンに移住し『過去と思索』の執筆を開始する。 過去を客観的に見つめなおして検討を加え 文章にすることが、現実への立ち直りの道でもあった。そして、異国にあって ロシアのためにできることは 言論による他はないのであるから、私財を投じて "自由ロシア出版所" を開設し、ロシアに向けての出版活動を開始する。それらの出版物は ロシアの知識人、民衆、そして皇帝でさえも読み、ロンドンのゲルツェンの家には トルストイ、ドストエフスキー、ツルゲーネフ、チェルヌイシェフスキー、そしてネチャーエフなども訪れる。 最も重要な出版物は、1857年に始めた雑誌『コロコル』であった。当初は月刊論説誌として、半年後には隔週刊、2年後からは週刊となって、ロシアばかりでなく、ヨーロッパにおける言論誌として重要な位置を占め、1867年までの 10年間に 245号を出した。1861年(日本は幕末の文久元年)には、1849年以来シベリアに送られて 独房と流刑の日々を過ごした アナーキストのバクーニンが脱走して、日本を経由して アメリカからロンドンのゲルツェンのもとに渡ると、『コロコル』誌が 彼の帰還を世界に告げ知らせたのである。 コロコル というのは "鐘" を意味するロシア語である。その誌名は、ゲルツェンの追放先であったこともある ノヴゴロド市の 鐘 に由来する。ペテルブルクの東南にある古都・ノヴゴロドは、中世において 共和政体の「自由都市国家」として栄えたのだが、15世紀に専制君主であるモスクワ大公・イワン3世によって征服され、政治的独立を失ってしまった。自治都市のシンボルであった ヴェーチェ(民会)の鐘は奪われ、戦利品としてモスクワに運ばれてしまう。しかし 自治都市を離れたこの鐘は、二度と再び 鳴ることがなかった。後に デカブリストの ルイレーエフは、この鐘を鳴らすことができれば 古代のロシアにあった民主制の伝統が よみがえるであろう、と訴えた。 かつて "雀が丘の誓い" で デカブリストの意思を引き継ぐことを決意したゲルツェンは、親友オガリョーフと共に 自由ロシア出版所の新しい言論誌を出すにあたり、 「二人だけで ヴェーチェの鐘を鳴らすのだ。 誰かがそれに答えるだろう」 と語って『コロコル』という名をつけ、ロシアとヨーロッパに自由と民主制を実現すべく、警鐘 を鳴らし続けたのである。 ゲルツェンは ロシアの農村共同体による社会主義を夢見たが、教条主義に陥ることは決してなく、人間の心理への深い洞察力をもった文学者でもあった。イギリスの思想史家・アイザイア・バーリンは次のように書いている。
次の ヴィトベルクの章に進む前に、ロシアの一人の芸術家について記しておきたい。 それはゲルツェンよりも6歳上の画家、アレクサンドル・アンドレーエヴィッチ・イワーノフ (1806-58) である。 きわめて優れた画家であったが、彼もまた デカブリストの乱に強く心を動かされ、ロシアの専制に対する批判精神を持ち続けた。美術学校 (アカデミー) の卒業制作で描いた『牢獄で賄方と酌人に夢を語るヨゼフ』は、"デカブリストの処刑と 皇帝の血の弾圧" を暗示したものとして批判され、ロシアにいづらくなる。

1855年に 皇帝ニコライが死に、アレクサンドル2世が帝位につくと、ロシアの状態は 多少改善されたかに見えた。そこで、その3年後にイワーノフは、ロシアの画壇を改革する希望をもって、帰国することを決意する。A・I・ゾートフの『ロシア美術史』(石黒寛、濱田靖子訳 1976 美術出版社)には 次のように書かれている。
1857年に イワーノフは ペテルブルクに帰り、チェルヌイシェフスキーや ツルゲーネフらに 暖かく迎えられたが、帝政ロシアからは冷遇され、批判された。 1858年、帰国から6週間後に コレラにかかり、不安と憂鬱の中で急逝したという。まだ 52歳であった。建築家・ヴィトベルクの死の3年後である。 |